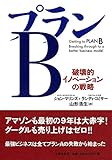おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。
今日は、会社における「パワハラ」口コミ投稿の違法性等に関する裁判例を見ていきましょう。
ICT・イノベーター事件(東京地裁令和7年1月15日・労判1334号63頁)
【事案の概要】
本訴事件は、Y社が、Xによるインターネット上の電子掲示板への2件の記事の投稿によりY社の名誉が毀損されていると主張して、Xに対し、不法行為に基づき、損害賠償金502万1500円+遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づき、上記各記事の削除を求める事案である。
反訴事件は、Xが、Y社に在勤中、Y社代表者からパワーハラスメントに当たる発言があったと主張して、Y社に対し、安全配慮義務違反による債務不履行に基づき、損害賠償金110万円+遅延損害金の支払を求める事案である。
【裁判所の判断】
1 Xは、Y社に対し、36万円+遅延損害金を支払え。
2 Xは、別紙1投稿記事目録1の「投稿内容」のうち、「パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」の部分を削除せよ。
【判例のポイント】
1 投稿内容「極論で言えば、命の危機で緊急搬送されても、命の危機を事前申告してくれないなら、有給にしませんと言う暴論を出してくるのは有り得ない。」
冒頭に「極論で言えば」との留保が付され、「有り得ない」との投稿者の意見で締めくくられている。このような本件記事を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として読めば、本件記事は、実際にY社において発生した事象について述べたものではなく、前記の事実を前提として、極論、すなわち極端な言い方をすれば、有給休暇の事後申請を認めないことは、たとえ命の危機で従業員が緊急搬送されたとしても事前申請がなければ有給休暇として扱わないという乱暴な論をいうようなものであるという意見ないし論評であると解される。
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事は、実際にY社において発生した事象について述べたものではなく、飽くまでもY社における取扱いを前提とした場合の極端な論を述べたものと読むことができる上、会社が有給休暇の事後振替を認めないことは何ら違法ではないことに照らすと、前記の意見ないし論評によりY社の社会的評価が低下するとは認められない。
2 投稿内容「社員に寄り添う風な事を謳っているが、その実中身は全然違うし、パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある。」
一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事のパワハラ部分は、Y社には職場内に長期間の精神的な治療を要する程度の強度のパワハラが存在するとの事実を摘示したものであると解される。
本件記事のパワハラ部分においては、具体的な言動の内容を示すことなく、単にY社の職場内にパワハラ等がある旨が記載された上で、そのために「場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」とパワハラ等により生ずる結果に関する記載がされている。そうすると、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件記事のパワハラ部分において、精神的な治療が長期間必要になる程度のパワハラ(すなわち何らかの言動等)が存在する旨が記載され、これは証拠等をもってその存否を決することが可能な事項であると理解されるものと解される。
したがって、本件記事のパワハラ部分について、単にY社におけるパワハラや偏見等により長期間の精神疾患の治療が必要となる従業員がいたという事実を前提とした意見ないし論評を表明したにとどまると解することはできない。
そして、本件摘示事実は、その内容に照らし、Y社の社会的評価を低下させるものと認められる。したがって、本件記事のパワハラ部分はY社の名誉を毀損するものである。
判例のポイント2の投稿内容の文頭に「極論を言えば」、文末に「と私は思う。あくまで個人的な感想であるが。」と追記したらどうなるでしょうか。
匙加減ひとつのような気もしますがいかがでしょうか。
日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。