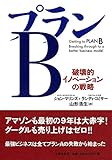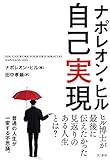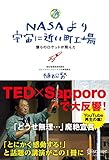あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今日は、本の紹介です。
「成功はアート、失敗はサイエンス」という言葉が登場します。
成功のしかたは人の数だけあるけれど、失敗のしかたは共通する、と。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「最も大切なのは組織全体で『失敗は悪ではなく、成長のための糧だ』という認識を共有することが不可欠です。失敗を個人の責任として厳しく追及するのではなく、なぜ失敗が起きたのかを客観的に分析し、次につなげる姿勢を奨励しましょう。」(425頁)
失敗を0にすることはできません。
どれだけ気を付けていても失敗してしまいます。
できるだけ同じ失敗をしないようにするためにはどうしたらよいかを考え、仕組み化する。
その繰り返しではないでしょうか。
それでも失敗はしますので。