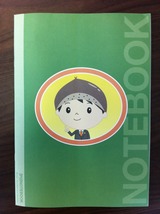おはようございます。
さて、今日は本の紹介です。

議論に絶対負けない法: 欲しいものを手に入れる「必勝のセオリー」
アメリカの弁護士が書いた本です。
この本は、今から15年以上前に出版された本を再編集したものです。
内容的には、かなりすっきりしたため、とても読みやすくなりました。
もっとも、最初に出された本を読んだことがある人は、この本を読むと、少し味気なく感じると思います。
さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。
「『一に準備、二に準備!』 私がそう言うと、若い弁護士は当てがはずれたような顔をする。彼らは労働を迂回できるような、楽な方法を知りたくて仕方がないのだ。しかし、本当の準備は労働などではない。
準備とは、創造する喜びだ。準備とは人生を苦労して前進すること、悩みながら生きていくこと、波にもまれながら生きていくこと、人生を生きることだ。
並はずれたIQを持っているが準備をするチャンスに恵まれなかった人よりも、力強い議論の準備を整えているふつうの人になりたい。
結局、天才とは脳細胞を決定したDNAのことを言うのではない。天才とはエネルギーだ。天才は準備で作られる。」(101~102頁)
心に響きますね。
準備とは、創造する喜びだ。
準備とは、人生を苦労して前進することだ。
準備とは、悩みながら生きていくことだ。
準備とは、人生とは波にもまれながら生きていくことだ。
準備とは、人生を生きることだ。
悩みながら進んでいくこと自体を楽しめるようになったら、もうひとつ上のステージに上がれるような気がします。
早くこの問題から解放されたいと考えるのではなく、徹底的に問題と向き合うことで見えてくることがあります。
問題から目を背けても何の解決にもならないことは経験上よくわかっています。
徹底的に向き合うしかないわけです。
もうひとつ上のステージに上がるチャンスと捉えることができれば、あとはやるべきことをやるだけです。