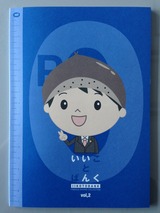おはようございます。
さて、今日は、試用期間としての有期常勤講師制度と雇止めの可否に関する裁判例を見てみましょう。
報徳学園(雇止め)事件(大阪高裁平成22年2月12日・労判1062号71頁)
【事案の概要】
本件は、平成16年4月に約1年間の雇用期限付で、Y社の美術科常勤講師として採用され、その後も、同様の雇用契約を2度にわたり締結していたXが、Y社に、19年度の雇用契約の締結を拒絶(雇止め)されたことに関し、それが雇用契約の更新拒絶に該当するところ、同更新拒絶には合理的理由がなく解雇権濫用法理の適用または準用により無効であると主張して、XがY社に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認および本件雇止め後である平成19年4月1日以降の賃金の支払を求めた事案である。
本件の争点は、本件雇止めの有効性である。具体的には、(1)本件各雇用契約に解雇権濫用の法理が適用または類推適用されるか、(2)解雇権濫用の法理の適用または類推適用が認められる場合、本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができないか、である。
なお、第一審は、Xの地位確認請求等を認容した。
【裁判所の判断】
雇止めは有効
【判例のポイント】
1 有期雇用契約が多数回にわたって反復更新されるなどして期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となり、当事者の合理的な意思解釈としては実質的に期間の定めのない契約を締結していたものと認定される場合、雇止めの意思表示は実質的には解雇の意思表示に相当し、その効力を判断するに当たり、解雇に関する法理を類推適用するときがある(最高裁昭和49年7月22日)。また、期間の定めのない契約と実質的に異ならないとまで認められない場合であっても、当該雇用関係がある程度の継続が期待されていたものであり、現に契約が何度か更新されているような場合、契約期間満了による雇止めには解雇に関する法理が類推されることがある(最高裁昭和61年12月4日)。そして、期間の定めのない雇用契約において、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、当該解雇権の行使は権利の濫用として無効となり(最高裁昭和50年4月25日)、上記類推適用の場合も同様と解されるが、ただ、期間の定めのない契約と実質的に異ならないとまで認められない場合には、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に締結された期間の定めのない労働契約における解雇とは合理的な差異がある(最高裁昭和61年12月4日)。
2 Y社の常勤講師制度が、専任教諭の実質的試用期間とするために設けられたとは認められない。このような期間の定めのある教員の雇用は、一般に、職員構成の変動のほか、年度ごとの生徒数や教科編成の変動等に対応するためと認めるのが社会の実態を反映したものであるが、本件において、常勤講師契約やY社の内部規則等に常勤講師契約が専任教諭採用の手段であることを示す規定がある等、Y社がこれと異なるものとして上記制度を導入したと認めるに足りる事情はない。Y社が、常勤講師としての勤務状況を判断材料として、その中から専任教諭を採用した実例があったことは事実であるが、このような実例があったことは、上記のような常勤講師の制度を採用した目的ないし有期雇用契約であることと矛盾しない。
3 ・・・このような経緯に照らすと、平成16年度雇用契約の時点では、Xが上記期待を持ったことの合理性があったかもしれないが、それは主としてB校長の言動に基づく主観的なものであって、常勤講師制度の目的等からの客観的根拠があったわけではない。そして、その後2年度にわたって専任教諭に採用されず、かえって、平成18年度雇用契約に先立ち、C校長及びG中学校長の上記告知を受け、さらに平成17年度限りで1名の常勤講師が雇止めとなったことを考慮すれば、少なくとも平成18年度には、Xの上記期待は減弱ないし消滅していたもの認めるのが相当であり、少なくとも合理的な根拠が乏しいものになっていたというべきである。
高裁で敗訴したXは、その後、最高裁に対し、上告受理申立てをしましたが、平成22年9月9日、不受理の決定が出されています。
本件では、Xの期待は主観的であり、客観的根拠があったわけではないとして法的に保護されるものではないという判断をされています。
雇止めに関する裁判例を相当数出てきており、企業が事前にかなり対策をとった上で、雇止めに踏み切っていることがうかがわれる事案も少なくありません。
本田技研工業事件がその典型ですね。
解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。