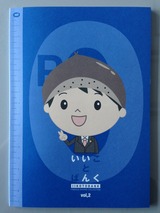おはようございます。
さて、今日は情報サービス会社部長に対する懲戒解雇等の有効性に関する裁判例を見てみましょう。
ブランドダイアログ事件(東京地裁平成24年8月28日・労判1060号63頁)
【事案の概要】
本件は、Y社のインタラクティブコミュニケーショングループ(ICG)2部の部長として雇用されたXが、平成22年4月にY社から受けた懲戒解雇処分が無効であるとして、Y社に対し、雇用契約上の地位確認および解雇後の賃金の支払いを求めるとともに、上記懲戒解雇に先立ち同年3月末に受けた降格・降給処分が無効であるとして、Y社に対し、上記部長の地位にあることおよび上記降格・降給処分前の地位にあることおよび上記降格・降給処分前の額である月額48万円の基本給の支払いを受ける地位にあることの確認ならびに賃金の支払を求め、さらに、上記懲戒解雇等がY社の不法行為に当たるとして、損害賠償を請求した事案である。
【裁判所の判断】
懲戒解雇は無効
降格・降給処分も無効
不法行為の成立は否定
【判例のポイント】
1 一般に降格・降給処分のうちでも、使用者が労働者の職位や役職を引き下げることは、人事権の行使として、就業規則等に根拠規定がなくても行い得ると解される。しかし、使用者が有する人事権といえども無制限に認められるわけではなく、その有する裁量権の範囲を逸脱したり、またはその裁量権を濫用したと認められる場合には、その降格処分は無効となるというべきである。特に、降格に伴って労働者の給与も減額されるなど不利益を被る場合には、その降格に合理的な理由があるか否かは、その不利益の程度も勘案しつつ、それに応じて判断されるべきである。
2 ・・・以上のとおり、Y社が本件降格・降給処分の理由として主張する具体的事実のうち、Xの責めに帰することができる事情は前記の宣伝メールに対する顧客からの苦情のみであって、他の事実についてはいずれもXの責めに帰するものと認めることはできない。しかも、上記宣伝メールの苦情といっても、どの程度広範囲の顧客に対し送信したかについては証拠上何ら明らかでないし、Xが、退会した顧客に対し故意にそのようなメールを送信する合理的な理由もないことからすれば、Y社が主張するように、これをスパムまがいと決めつけることは、およそ行き過ぎというべきである。
他方で、本件降格・降給処分により、Xは、部長職から一般職員に降格され、役職手当相当額5万円を減額されている。この5万円という減額幅は相当に大きいものといわざるを得ず、Xの部長職からの降格がかような給与減額を伴う処分であることからすれば、使用者固有の権限としての人事権の行使といえども、相応の合理性が要求されるというべきであって、そのような合理性が認められない場合には、過度に不利益を課すものとして、裁量権の濫用に当たるというべきである。
しかるに、本件降格・降給処分の理由としてXの責めに帰すべき事情と認められるのは前記の限度であって、これのみでは、上記のような大きな不利益を伴う本件降格・降給処分の合理性を基礎付けることはできないというべきである。・・・したがって、本件降格・降給処分は、裁量権の濫用というべきものであって、これを無効と認めるのが相当である。
3 使用者による懲戒権の行使は、企業秩序維持の観点から労働契約関係に基づく使用者の権能として行われるものであるが、就業規則所定の懲戒事由該当事実が存する場合であっても、当該行為の性質や態様等の状況に照らし、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当性を欠くと認められる場合には権利の濫用に当たるものとして無効になる(労働契約法15条)。特に、懲戒解雇は、労働者にとって最も厳しい制裁手段であり、多くの局面で当該労働者に不利益を与えるのが実情であることにかんがみれば、上記の権利の濫用に当たるか否かについては、その行為により使用者側が受けた被害の重大性、回復可能性はもとより、そのような行動に出た動機や行為態様を子細に検討した上で判断する必要があるというべきである。
4 ・・・以上にみたように、Xの本件顧客リスト送信行為が、Y社就業規則所定の懲戒事由に該当する行為であることは否定できないものの、その動機がY社における営業を推進するためであって不正なものとはいえないことや、Y社に実害が生じていないことなどをはじめとする諸事情を総合考慮すれば、Xを懲戒解雇に処することは酷に失するといわざるを得ない。したがって、本件懲戒解雇は、社会通念上相当であるということはできないから、懲戒権の濫用に当たり、無効と認めるのが相当である。
解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。